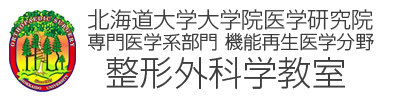研究紹介
1.早期変形性関節症(OA)の病態解明
「一度変性が開始すると二度と元には戻ることはない」と言われる軟骨の退行変性ですが、組織学的な破壊が生じる前段階で軟骨の糖鎖が変化することを私たちの研究グループは解明しました。糖鎖とは核酸やタンパク質に続く”第三の生命鎖”として知られ、全ての細胞表面は糖鎖分子によって覆われており、癌、慢性疾患、感染症、免疫・脳・発生などの異常、老化などその影響は多岐に及びます。軟骨と糖鎖との関連について国内で最も多くの実績を有しており、OA予防に向けた次の段階へ進んでいます。

2.関節軟骨損傷の早期診断法を目指したモダリティー開発研究
初期の軟骨損傷は可塑性があると考えられていますが、既存の検査法では初期病変を捉えることは極めて困難です。私たちの研究グループは、酸素の安定同位体である17-Oで標識された水を関節内造影剤として投与しMRI撮像することで、損傷軟骨での水の代謝動態を可視化し、微細な軟骨損傷を捉えることに成功しました。また、より詳細な病態解明のため、同位体顕微鏡を用いた研究にも取り組んでいます。

図:ウサギ大腿骨膝関節面
軟骨損傷部(左図 矢印)に一致してMRIでの信号変化(右図 矢印)が認められる。
3.小児骨端線損傷研究
小児骨端線損傷は変形治癒により、四肢の短縮、変形をきたすため社会的に重要な問題と認識されています。しかしながら現状の治療法は損傷部の外科的手術しかなく、小児に大きな負担を与えます。私たちの研究グループは、マウス骨端線損傷モデルを用いた分子生物学的研究に基づき、世界初の骨端線損傷に対する非侵襲的治療法の開発に取り組んでいます。

図:(左)マウス脛骨近位骨端線損傷後の野生型マウスとノックアウトマウスの組織学的解析。ノックアウトマウスでは損傷部の骨橋形成が阻害される。(右)脛骨短縮率。ノックアウトマウスでは変形治癒が予防される。